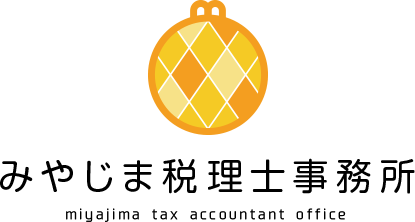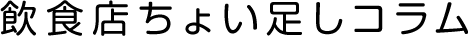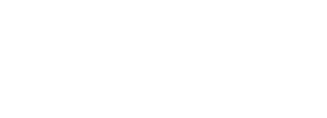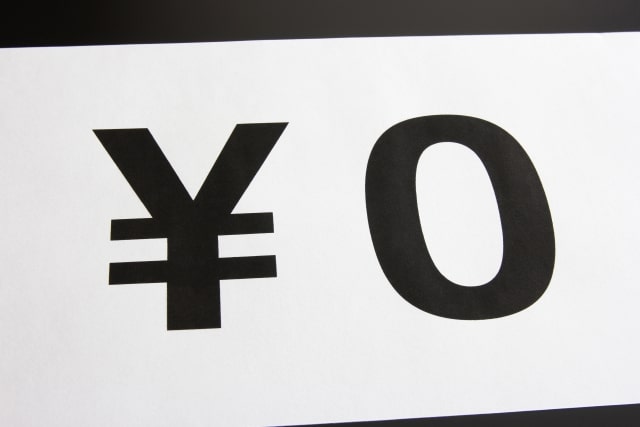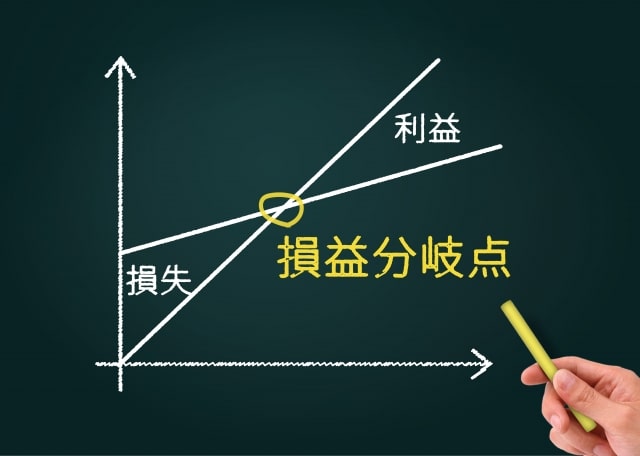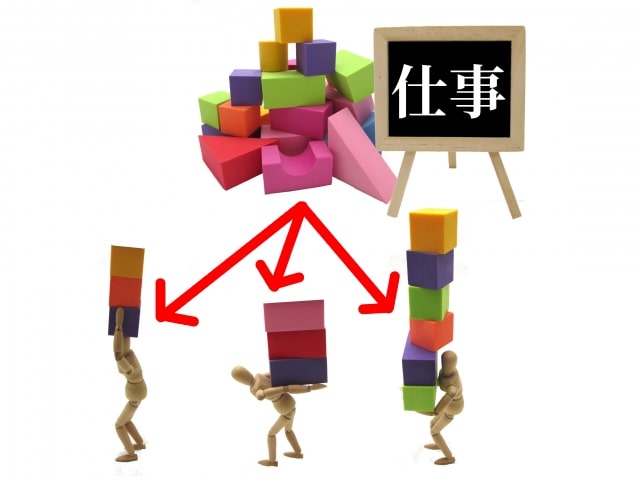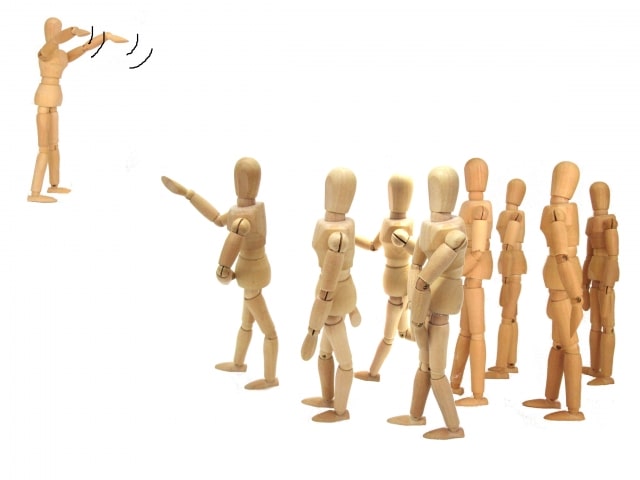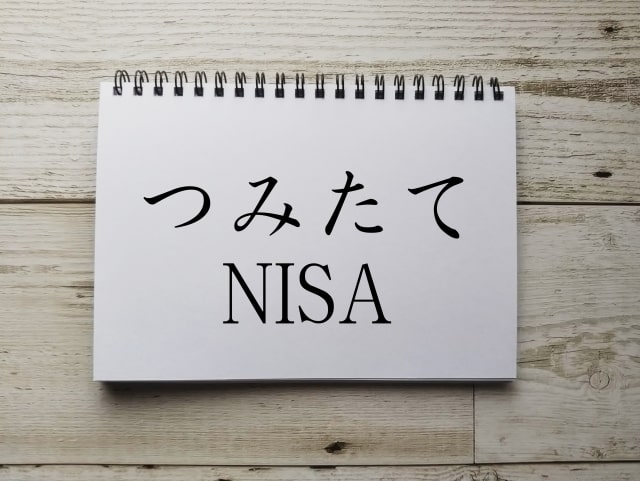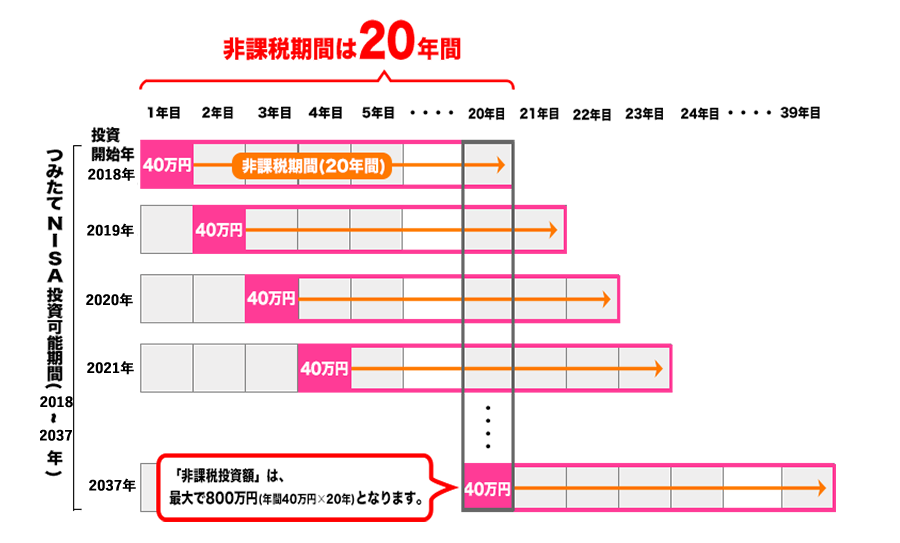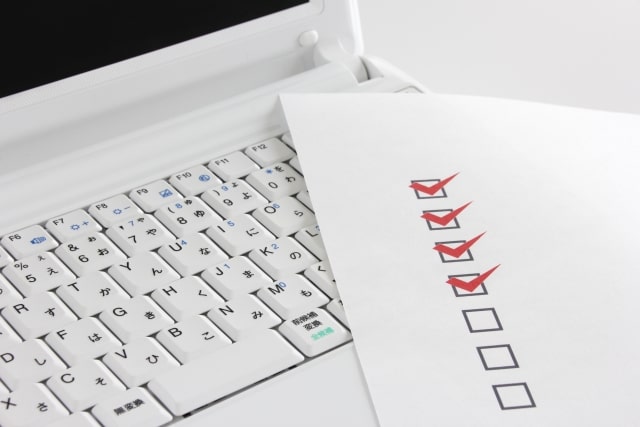



2022.08.29 決算・節税対策
飲食店経営者のための小規模企業共済の加入手続き
節税や退職金の積み立てとして人気が高く、おススメされることが多い小規模企業共済です。 将来的な資産形成として大いに役に立ち、なおかつ一定期間継続すると元本割れがない安全資産であるため、私も資産形成の優先順位の一番としておススメしております。 今回は具体的にどのようにすれば小規模企業共済に加入できるか、という手続きのご案内です。小規模企業共済はサラリーマンでは加入することができません。 経営者である必要があるのですが、そのほかにも業種ごとの従業員数の要件があります。 飲食店の場合、個人事業主・法人問わず、常時使用する従業員の数が5名以下である必要があります。 なお、この場合の従業員の数には、事業主本人、家族従業員などは含まれません。 要件は中小企業基盤整備機構のHPに記載してあるので、よくご確認いただき、不明な点がある場合はコールセンターへお問い合わせください。加入資格を確認したら、加入手続きの流れを確認しておきましょう。 ①申込書の請求 ②書類の記入 ③窓口へ提出 ④書類の受取り という流れになります。 書類の記入例は契約申込書と一緒になっているので、記入例の通りに書けばよいです。 申し込みをする先は、業務委託契約を結んでいる団体または金融機関の窓口となります。 代理店一覧をWEB上で確認することができますが、メガバンク、地銀、信用金庫であれば主要なところは代理店になっているケースが多いです。 (北海道であれば、北洋、道銀、北海道信用金庫など。メガバンクもOKです)加入資格があることを確認し、契約の流れを確認したら、契約申込書を請求します。 こちらも中小企業基盤整備機構のHPの資料請求フォームから請求すると、郵便で送られてきます。書類を記入し、添付書類を準備します。 個人事業主であれば確定申告書の控え。開業したばかりであれば開業届の控えが必要です。 (これらの書類は税務署の受付印、電子申告の場合はメール詳細が必要です) 法人の場合は3か月以内に交付された法人・商業登記簿謄本の原本が必要です。 (登記簿は法務局で取得することができます) 記入した契約申込書と添付書類、念のため銀行印を持って銀行窓口に行き手続きをします。小規模企業共済にはコールセンターが設けられています。 このコールセンターは問い合わせが多いのか人数が少ないのか、つながりにくいこともありますが、加入の要件、書類の書き方、必要書類など詳しく教えてもらえます。 加入手続きには時間がかかるため、その年の所得控除を受けたい場合は早めに手続きを進めた方がよいでしょう。 ちなみに小規模企業共済掛金控除は物的控除であるため、その年中に支払った分のみが控除の対象となります。 年末に近いタイミングなどでその年に控除を受けたい方は、初回の掛金払い込みを窓口で支払う、掛金を年払いするなどの方法をとるのがおススメです。